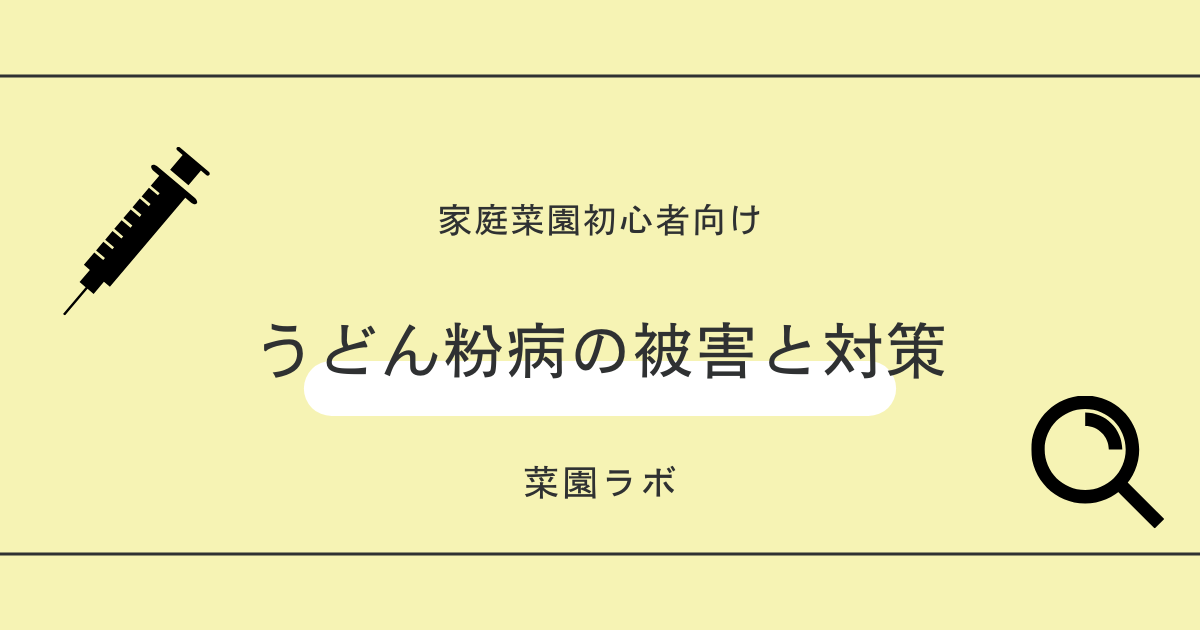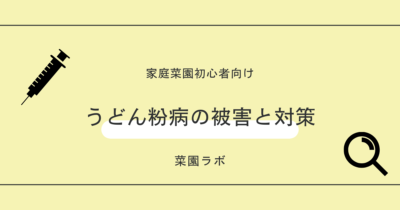- うどんこ病が発生する原因
- うどんこ病の予防方法
- うどんこ病の治療方法
様々な野菜に発生し粉を吹いたように白くなり、酷くなると実にも発生します。
予防には竹酢液を50倍に水で薄めたスプレーが効果的ですが治療効果はありません。
農薬での治療はカリグリーンが効果的。
うどんこ病の被害状況と発生する原因




- 気温:24度~32度
- 時期:5月~11月頃
- 白い粉を吹いたような症状が出る
- 進行すると葉が黄色くなったり、縮れたり、枯れたりする
- 発生がひどくなると茎や花などにも発生する
- 風で胞子が飛ばされ伝染
- 原因のカビが土や枯葉に残留しており発生
うどんこ病は家庭菜園をしているほとんどの人が経験する可能性が高い病気です。
特にトマトやキュウリなどで非常に頻繁に発生し、葉にうどん粉をまぶしたような状態になることからその名が付けられています。
初期の段階では、薄く点々が見られる程度ですが、進行すると葉全体に広がり、隣接する他の植物にも広がることがあります。さらに重症化すると茎や花にも感染し、早急に対策や処置を行う必要があります。
一般に梅雨時に発生すると思われがちですが、実際には乾燥している時に最も繁殖が進み、雨が降ると胞子が舞いにくくなるため、発生が抑えられます。
うどんこ病はカビが原因で引き起こされる病気ですが、異なる野菜の間では感染は広がりません。
このカビは越冬性があり、感染した葉を処理せずに土に混ぜると、土壌に残留した菌が翌年の作物に影響する可能性があります。
風に乗って胞子が広がるため、同じ畑内での管理が重要です。早期の対策が発生の抑制につながります。
うどんこ病の被害が出る野菜
こんな野菜にうどんこ病は発生しやすいです。
【発生前】うどんこ病の防除・予防対策
- 無農薬で出来る予防法
- 農薬を使う予防法
病気が発生する前に出来る「無農薬で出来る要望策」「農薬を使った予防策」を紹介します。
(無農薬)防除・予防方法
- 泥はね対策(マルチをする)
- 密植を避ける日当たりや風通しを良くする
- 窒素肥料の多い肥料を与えすぎない
- うどんこ病に対抗性がある品種を選ぶ
- 輪作する
- 自作のスプレーをする
水はけと泥はね対策


カビ菌が土壌に潜んでおり、そのカビを含んだ土が雨などで跳ね返り葉で発生することもあるのでビニールマルチや敷き藁マルチはおすすめです。
水はねを防ぐためには、マルチシートの使用が効果的です。
密植されているなど葉が重なったり、風通しが悪いと伝染しやすいので植え付けの際に株間を守って植える事や栽培中の葉の管理も適切に行う必要があります。
窒素肥料の多い肥料を与えすぎない


また、窒素が過剰に溶け出す心配のない肥料を使うことをおすすめします。
マイガーデンベジフルは、窒素成分が多くないため、家庭菜園でおすすめの追肥としても使える肥料です。
耐性のある品種を使う
種子からも伝染するので、毎年同じ種を使わず新しい種を使います。
また、抵抗品種も発売されているのでその品種を使う事もオススメです。
例えばキュウリは、おいしさ一番星(トーホク)などです。
輪作をする
うどんこ病の菌は同じ野菜を同じ場所で育てると土に残っていた菌で発生しやすい事もあるので輪作をして連作をさけるのがおすすめ。
うどんこ病予防の無農薬自然派スプレー
- 木酢液・竹酢液スプレー
- ストチュウ
- 重曹スプレー
身近な物で作る自然派スプレーは農薬では無いので定期的(1週間や2・3日単位)で散布を継続しないと効果が出ないので注意。
酢と重曹、どちらがうどん粉病の治療や予防に効果的かについて議論があります。
結論から言うと、どちらも治療効果はなく、予防効果も限定的です。健全な葉の状態であっても、週に1回または2回、散布しなければ予防できません。
うどん粉病が発生した葉にスプレーをかけると、一時的に治ったように見えることがありますが、実際には菌が葉に残っており、再発する可能性があります。
特に効果的とされるのは、「ストチュウ」として知られる、酢にニンニクや唐辛子を加えた溶液です。竹酢液を50倍に薄めて使用すると、より効果的な予防が期待できます。
木酢液や通常のお酢に関する研究は見当たりませんが、竹酢液を使用した場合には、50倍で薄めることで予防効果があるという報告があります。100倍では効果が限定される可能性が示されています。
具体的なスプレーの作り方は下記ページにて紹介しています。
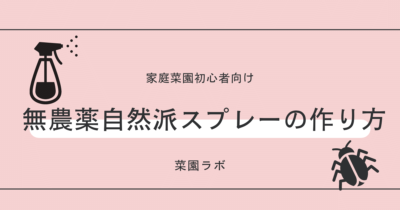
(農薬)防除・予防方法
- ベニカXスプレー
- ベニカXファインスプレー
農薬は、同じ病気や害虫に対しても、使用できる野菜の種類が決まっています。そのため、野菜ごとに使用する農薬を分ける必要があります。
農薬を購入・使用する前に適用作物を確認し、その作物に適した薬剤を選びましょう。農薬は劇薬であるため、子供の手の届かない場所に保管してください。
スプレータイプはベニカXスプレー、ベニカXファインスプレーが手軽です。
【発生後】うどんこ病の治療方法と対策


- 太陽熱消毒で菌を殺す
- 天地返しをして菌を遠ざける
畑の中で土にすき込むと、土に菌が残り、翌年に再発したり、他の野菜に広がる原因となるため、必ず外に持ち出します。
うどん粉病の菌は太陽熱の高温で死滅するため、「太陽熱消毒」は家庭でできる有効な方法です。ただし、土の温度が十分に上がる夏にしか行えないので注意が必要です。
うどん粉病が発生した葉は、初期の段階でスプレーなどを使い、1週間ほど様子を見ることもできますが、胞子が他の葉に広がる恐れがあるため、早めにカットして畑の外に持ち出し処分します。
冬には、春・夏野菜の栽培に向けて、スコップで表層(15~30cm)の土を深度(50~60cm)の土と入れ替える「天地返し」が効果的です。
発生した場所に次に野菜を植える際には、再発を防止するための対策を講じましょう。
(農薬)治療方法
- カリグリーン
うどん粉病におすすめの農薬を紹介します。
農薬は、同じ病気や害虫に対しても、使用できる野菜の種類が決まっています。そのため、野菜ごとに使用する農薬を分ける必要があります。
農薬を購入・使用する前に適用作物を確認し、その作物に適した薬剤を選びましょう。農薬は劇薬であるため、子供の手の届かない場所に保管してください。
有機栽培(有機JAS)にも対応しているカリグリーンが発生初期なら家庭菜園ではおすすめです。