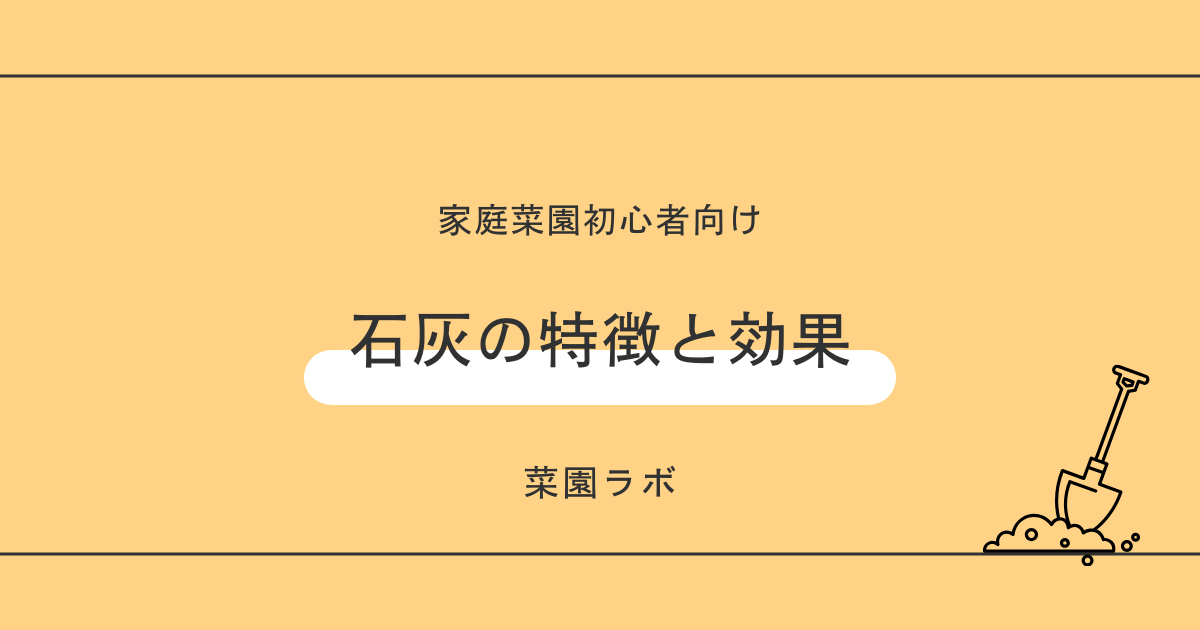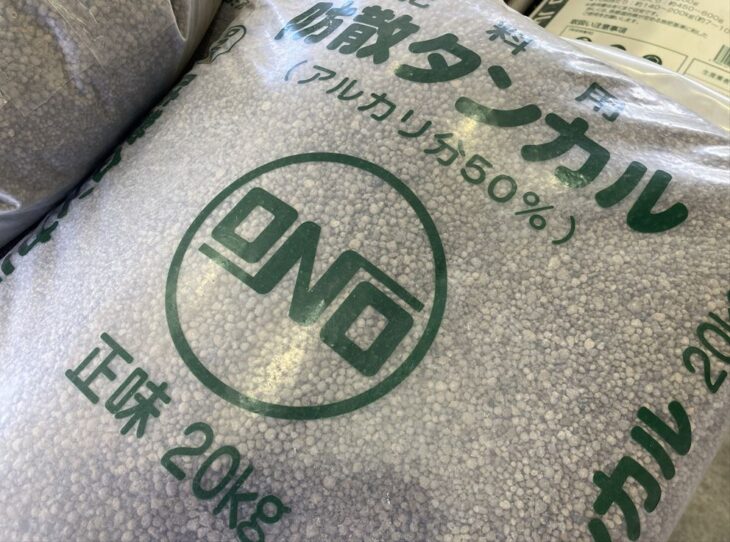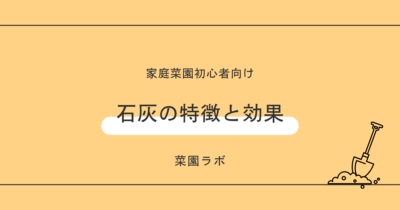- 石灰の種類の違い
- 撒いてすぐに植えられる石灰の種類
- 石灰(カルシウム)を補給する意味
石灰は土壌改良に使いますがPH調整以外にも色々効果があります。
有機石灰は植え付け1週間前に肥料と一緒に、苦土石灰をは植え付け2週間前に堆肥と一緒に与えましょう。
苦土石灰ならマグネシウムが補給できるので急ぎの人以外は苦土石灰もおすすめ。
家庭菜園で使う石灰の種類の違い
| 家庭菜園 | すぐ植え付け | マグネシウム【苦土】 (Mg) | 微量要素 | 別名・種類 | 成分 | メリット | デメリット | 使用量 | アルカリ性 | カルシウム (Ca) | 効き目 | 価格 | 100均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生石灰 | ー | 酸化カルシウム | アルカリが非常に強いので即効性 | 目に入ると失明の可能性 | 30~100g/㎡ | 700円 | ||||||||
| 消石灰 | ー | 水酸化カルシウム | アルカリが非常に強いので即効性 | 目に入ると失明の可能性 | 50~100g/㎡ | 855円 | ||||||||
| 炭カル | 肥料と混ぜなければ可能 肥料と混ぜるなら1週間あける | タンカル | 炭酸カルシウム | pH調整のみ出来る | マグネシウム補給は不可 | 50~100g/㎡ | 498円 | |||||||
| 苦土石灰 | 肥料と混ぜなければ可能 肥料と混ぜるなら1週間あける | 苦土カル 炭酸苦土石灰 | 炭酸カルシウム 炭酸マグネシウム | マグネシウム補給が可能 | 特になし | 100~200/㎡ | 440円 | |||||||
| 有機石灰 | カキ殻石灰 ホタテの殻石灰 卵の殻など | 炭酸カルシウム | 肥料・堆肥と一緒に混ぜて撒ける 微量要素を補給できる | アルカリ性が弱く pH補正は穏やか | 50~300g/㎡ | 420円 |
- 価格はホームセンターで調査した取り扱い(20㎏)での価格
- 成分やアルカリ度数は参考値なので商品毎に違いがある
- 使用量は参考値なのでパッケージを参照する事
- 生石灰
- 消石灰
- 炭カル
- 苦土石灰(苦土カル)
- 有機石灰(カキ殻石灰など)
それぞれの石灰の違いを詳しく解説します
生石灰
- 主成分(別名)・・・酸化カルシウム
- アルカリ性・・・95%
家庭菜園では生石灰は使用しません。
生石灰は水と混ざると100度近くまで発熱する特徴があり、食品の乾燥剤にも利用されている成分です。
粉が飛んで目に入ると失明の恐れがあるため、取り扱いには十分な注意が必要です。
消石灰
- 主成分(別名)・・・水酸化カルシウム
- アルカリ性・・・72%
- 植え付け・・・肥料と一緒にまかない。植え付け2週間前。
消石灰は、以前は小学校のライン引きに使用されていましたが、生石灰と同様に目に入ると失明の危険があるため、現在では使用されていません。
強いアルカリ性を持つ消石灰は、粘膜や皮膚に触れるとさまざまな化学的な外傷を引き起こします。
また、アルカリ度が高く、酸性に傾いた土壌を強力に中和しアルカリ性に変える即効性がありますが、私は家庭菜園での使用をおすすめしません。
炭カル(タンカル)
- 主成分(別名)・・・炭酸カルシウム
- アルカリ性・・・50%
- 植え付け・・・肥料と一緒に撒かない。植え付け2週間前。
炭カル(タンカル)は、炭酸カルシウムを含み、土壌のpHをアルカリ性に補正する効果があります。
次に紹介する苦土石灰と基本成分は同じですが、炭カルには炭酸マグネシウムが含まれていないため、微量要素であるマグネシウムの補給はできません。
家庭菜園では、マグネシウムを補給せずに土壌のpHだけを改善したい場合に、炭カルが適しています。
苦土石灰(苦土カル)
- 主成分・・・炭酸カルシウムと炭酸マグネシウム
- 別名・・・炭酸苦土石灰/苦土カル
- アルカリ性・・・55%
- 植え付け・・・肥料と同時に撒けない。植え付け2週間前。
家庭菜園でよく使われる資材の一つが、苦土石灰です。
この苦土石灰には、炭カル(炭酸カルシウム)と炭酸マグネシウムが含まれており、土壌のpH調整に加え、マグネシウムの補給も可能です。
なお、苦土石灰を「苦土石灰単独」で与える場合、植え付け作業をすぐに行っても問題なく、また追肥のように使っても根に悪影響を与える心配はありません。
しかし、「肥料」と一緒に使う際には注意が必要です。肥料に含まれる「葉を育てる成分である窒素(N)」と反応してアンモニアガスが発生し、窒素不足や酸素不足を引き起こすことがあります。
そのため、せっかく肥料を施しても窒素成分が失われてしまうリスクがあるため、「肥料と一緒に撒く場合は、肥料を施す1週間前、苗の植え付けの2週間前までに苦土石灰を施す」ようにしましょう。
有機石灰(カキ殻石灰・卵の殻など)
- 主成分・・・炭酸カルシウム
- 別名・・・カキ殻石灰・卵の殻など
- アルカリ性・・・46%
- 植え付け・・・肥料と同時に撒ける。植え付け当日可能。
家庭菜園で苦土石灰と同様に多く使用されるのが有機石灰です。
有機石灰には、主成分によってさまざまな種類がありますが、特に牡蠣やホタテの殻を粉末にした『カキ殻石灰』や『ホタテ貝殻石灰』と呼ばれるものが一般的です。また、卵の殻を主成分とする石灰もあります。
貝殻系の石灰には、マンガン、ホウ素、亜鉛、銅、鉄、モリブデンなど、海由来のミネラルを含む微量要素が豊富に含まれているのが特徴です。これらの微量要素によって、葉や茎が元気に育ち、病気にかかりにくくなるといったメリットがあります。
さらに、有機石灰は肥料と一緒に施せるため、植え付け当日に肥料と一緒に撒くことが可能です。
土壌を穏やかに中和し、アンモニアガスなどもほとんど発生しないため、植え付け時期が限られている場合にも家庭菜園に最適です。その効果は緩やかに持続します。
石灰の成分は炭酸カルシウムが主成分!
- カルシウム欠乏・・・病気になりやすい、枯れたりする
- カルシウムのメリット・・・根が大きく成長、生育がよくなる、収穫量UP
どの種類の石灰にも共通する特徴は、主成分が炭酸カルシウムである点です。石灰は単に畑の酸度を酸性からアルカリ性に調整するためだけでなく、カルシウムの補給源としても用いられます。
カルシウムが不足すると、トマトが尻腐れ病を発症したり、キャベツの心葉の生育が阻害されて内側に巻き込むようになったり、シュンギクの先端が黒褐色になって枯れたり、イチゴの新葉の先端が茶色く変色するなど、成長点や葉先に症状が現れます。
また、カルシウムは水に溶けやすく、土の奥深くまで浸透して作物の根の成長を促進し、生育を助ける効果もあります。例えば、ジャガイモの収穫量が増えたり、キャベツが均一に成長したり、トウモロコシの実が太く育つといったメリットが期待できます。
石灰を畑に撒く理由は酸度(PH)調整のため!
- 即効性・・・消石灰・生石灰
- 遅効性・・・炭カル・苦土石灰・有機石灰
石灰を畑に撒く主な理由は、土壌の酸度を調整するためです。日本は雨が多い国であり、降雨によって畑の土壌は酸性に傾きやすくなります。そのため、何も手を加えない畑の土は通常、酸性です。
野菜には酸性を好む作物とアルカリ性を好む作物があり、ほとんどの野菜はアルカリ性もしくは中性の土壌を好みます。したがって、石灰を撒いて土壌をアルカリ性に近づけ、適切な酸度で野菜を育てることが重要です。
これは、土壌がアルカリ性か酸性かによって、野菜が吸収できる栄養素が変わるためです。
例えば、酸性の土壌ではカルシウム、マグネシウム、リンなどが不足しやすくなります。一方、アルカリ性の土壌ではマンガンや鉄が不足しやすくなります。
野菜ごとに適した酸度がありますが、基本的にはpH6.0~6.5を目指せば問題ありません。目分量ではなく、酸度計を使って正確に測定することが大切です。
土づくりで石灰を畑に散布するタイミング
- 石灰と肥料を同時に撒きたい人・・・有機石灰(カキ殻石灰・卵の殻石灰など)
- 石灰と肥料をわけて撒く時間がある人・・・タンカル/苦土石灰
苦土石灰を使う場合
| 2週間前 | 1週間前 | 当日 |
|---|---|---|
| 完熟堆肥、苦土石灰 | 肥料 | 植え付け |
有機石灰を使う場合
| 2週間前 | 1週間前 | 当日 |
|---|---|---|
| 完熟堆肥 | 肥料、有機石灰 | 植え付け |
土づくりで必要な「堆肥・石灰・肥料」を撒く順番は、基本的に「植え付け3週間前に堆肥、2週間前に石灰、1週間前に肥料を撒いて植え付けを行う」のがベストとされています。これは消石灰を使う場合のスケジュールです。
「堆肥と石灰を同時に撒いても良いのか?」という疑問については、消石灰はアルカリ性が強いため、アンモニアを多く含む未熟な堆肥や肥料と一緒に使用すると、アンモニアガスが発生してしまいます。そのため、消石灰と堆肥・肥料は1週間ほど間隔を空けて施す必要があります。
一方で、完熟堆肥や苦土石灰を使用する場合は、堆肥と一緒に混ぜても問題ありません。ただし、苦土石灰でも肥料は、間隔を空ける必要があります。
なお、家庭菜園では植え付け可能な日や準備できる日が限られている場合があります。そんなとき、土づくりを急ぐ方に役立つのが、有機石灰です。
植え付けがすぐ出来るのはかき殻石灰など有機石灰!
有機石灰である「カキガラ石灰・ホタテ貝石灰・卵の殻石灰など」は、アルカリ成分が控えめで効果が穏やかです。また、アンモニアガスもほとんど発生しないため、元肥として肥料と一緒に撒くことが可能です。
限られた時間で作業する家庭菜園には、これらの有機石灰が特におすすめです。
また、「植え付けの1週間前に完熟堆肥・有機石灰・肥料を一度に撒く」ことで、1日で土づくりの準備を整えることもできます。植え付け当日にこの3つをまとめて撒く方法もありますが、土に馴染んで肥料効果が現れるまでに時間がかかるため、できれば1週間前に準備をしておくと失敗が少なく、野菜も順調に育つでしょう。
土壌改良以外の石灰の使用方法!
- ジャガイモの切り口に使う?
- キュウリなどのうどん粉病に効く?
- トマトなどの尻腐病の解消ができる?
石灰を使った土壌改良以外の用途でよくある疑問点をまとめます。
ジャガイモの切り口につけて植える
石灰資材としては一般的に紹介されませんが、肥料効果のある「草木灰」はアルカリ性成分を多く含んでおり、苦土石灰のように土壌をアルカリ性にする性質があります。
また、ジャガイモの種芋を植え付ける際、乾燥時間が取れない場合には、草木灰を切り口に薄くまぶすことで、切り口の殺菌効果が期待でき、腐敗防止に役立ちます。
キュウリ等のうどん粉病に効果?
石灰や草木灰は、うどんこ病の対策として、白い粉が発生した野菜にバラバラとふりかけることで、野菜が元気になることが知られています。
ただし、経験上、これらがうどんこ病を改善・治療できるわけではなく、「ごく初期のうどんこ病や予防に効果がある程度」と言えます。
トマトなどの尻腐病の解消ができる
うどん粉病と同様に、石灰を葉に振りかけることで尻腐れ病の予防効果が得られます。
尻腐れ病はカルシウム欠乏によって発生する生理的障害であり、病気ではありません。そのため、石灰を用いることでカルシウムを補給し、改善することができます。
また、葉に振りかけるだけでなく、土壌にしっかりとすき込むことで、カルシウム不足から生じる尻腐れ病を予防できます。したがって、土づくりの段階で石灰を加えること(カルシウム補給)は非常に重要です。
石灰はホームセンター以外で100円ショップでも買える!
石灰の購入場所として候補に挙げられるのは「ホームセンター」と「100円ショップ」です。
ダイソーやセリアでは「苦土石灰」のみを販売しており、500gや600gと比較的多い量が100円で手に入ります。そのため、自分が育てている野菜に必要な量が100円ショップで足りる場合、こちらも選択肢となるでしょう。
ただし、有機石灰(牡蠣殻など)は100円ショップには取り扱いがないため、ホームセンターや通販で購入することをおすすめします。
家庭菜園の石灰でよくある質問Q&A
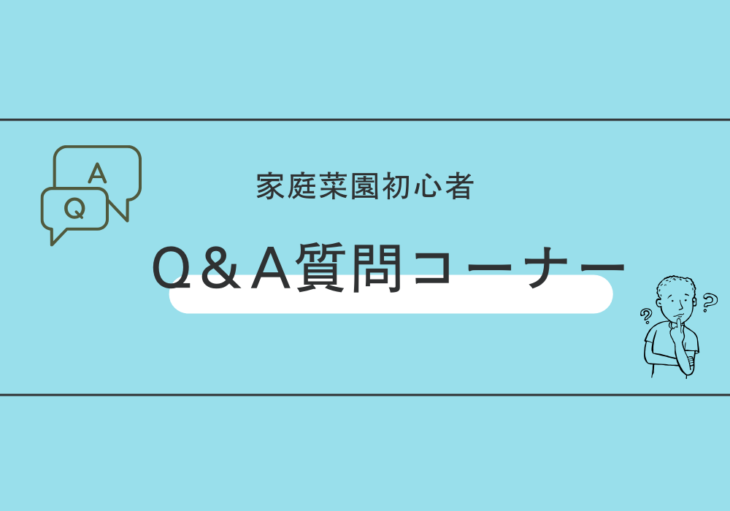
石灰で初心者が疑問に思う内容を質問形式でまとめています。
石灰の質問一覧
質問クリックすると該当箇所にジャンプ!
苦土石灰と石灰の違いは?
- 苦土石灰と石灰の違いは?
-
苦土石灰は石灰の一種です。家庭菜園で使用される石灰には、苦土石灰のほかに有機石灰(カキ殻石灰、ホタテ貝石灰、卵の殻石灰など)や炭カル(タンカル)などがあります。苦土石灰は、他の二種類の石灰と比べてマグネシウム(苦土)を補給できる点が特徴です。
石灰と草木灰の違いは?
- 石灰と草木灰の違いは?
-
苦草木灰は草木を燃やした際にできる灰で、肥料として利用されます。しかし、アルカリ性であるため、石灰と同様に土壌をアルカリ性に傾ける効果があります。石灰はカルシウムの補給と土壌のアルカリ化を促す資材です。
石灰に除草効果や雑草対策の効果がある?
- 石灰に除草効果や雑草対策の効果がある?
-
石灰を施すことで土壌がアルカリ性に傾き、スギナなどの酸性土壌を好む雑草が減少することがありますが、除草効果や雑草対策としては不十分です。石灰窒素という肥料があり、その中に含まれる除草成分シアナミドには一年草の雑草を抑制する効果があります。したがって、雑草対策には石灰ではなく石灰窒素を使用すべきです。
石灰窒素は農薬として登録されている肥料で、センチュウや根こぶ病の防除にも利用できます。しかし、石灰窒素のデメリットとして、シアナミドが散布後に肥料成分に変わるまでの間は植え付けができない点があります。したがって、散布後は植え付けまでに10日間の間隔を空けることが推奨されます。
石灰を撒くと土が固くなる?
- 石灰を撒くと土が固くなる?
-
家庭菜園でおすすめしている苦土石灰と有機石灰は、緩やかにpH調整効果があるため、基本的な使い方では土が固くなることはありません。ただし、与えすぎるなどの過度な使用をすると、土が固くなることもあります。家庭菜園ではおすすめしませんが、消石灰や生石灰は即効性がありますが、アルカリ性が強いため土が固くなる傾向があります。
石灰で土壌改良ができる?
- 石灰で土壌改良ができる?
-
石灰を使用することで、土壌の改良が可能です。これは土壌のpH調整やカルシウムの補給につながります。さらに、有機石灰を用いると微量要素のミネラルも補給でき、苦土石灰を使用すればマグネシウムの補給が行えます。
石灰を撒きすぎるとどうなる?
- 石灰を撒きすぎるとどうなる?
-
石灰を撒きすぎると、土壌がアルカリ性に傾きすぎて野菜に適した環境ではなくなり、微量要素を吸収できない状態になります。また、土が固くなるなどのデメリットもあります。まずは、購入した石灰の袋を確認し、自分の畑のサイズを正確に測定して適切な量を撒くことが何よりも大切です。もし撒きすぎた場合は、雨が降れば土壌が徐々に酸性に戻るため、石灰を追加せずに様子を見てください。酸度計を使って土壌の酸度を測定し、多少撒きすぎても問題ないように効果が穏やかな有機石灰を使用することをおすすめします。
石灰とジャガイモにつける?
- 石灰とジャガイモにつける?
-
ジャガイモの種芋を植え付ける際には、切り口を乾燥させることが重要です。乾燥させずに防腐処理を行う方法として「草木灰」を使用する方法があります。草木灰は石灰と同様に土壌をアルカリ性に傾けますが、石灰そのものではありません。また、草木灰は肥料成分を多く含んでいるため、肥料としても利用される資材です。
石灰と木酢液の相性は?
- 石灰と木酢液の相性は?
-
家庭菜園で使用する苦土石灰や有機石灰は、アルカリ性が弱いため、特に混ぜて使用しても問題ありません。また、木酢液を葉面散布する際に苦土石灰を混ぜることで、トマトの尻腐れ病や灰色かび病の発生が少なくなるという報告もあります。
粉の石灰と粒状の石灰の違いは?
- 粉の石灰と粒状の石灰の違いは?
-
石灰には粉状タイプと粒状タイプがあります。一般的に、粒状の方が撒きやすく便利で、効果はどちらも変わりません。
粉状タイプを土壌に撒く際は、苦土石灰や有機石灰が目に入ったり、皮膚に直接触れると、皮膚が荒れたり、かぶれることがあります。そのため、マスク、眼鏡、手袋を着用し、吸い込まないように注意しましょう。また、小さなお子様が周囲にいないか確認することも重要です。
石灰の捨て方は?
- 石灰の捨て方は?
-
生石灰を含む小さい乾燥剤は、基本的には燃えるゴミとして処分できるでしょうが、お住まいの自治体によって異なるため、心配な場合は事前に問い合わせをしましょう。
生石灰は水と混合すると発熱する性質があるため、水分の多い物と一緒に捨てる際は注意が必要です。一方、苦土石灰や有機石灰など、家庭菜園で使う石灰は発熱しません。
私が石灰を処分した際には、畑ではなく家の砂利の通路に撒き、ホースで水をかけて溶かしました。
まとめ
- 家庭菜園は苦土石灰か有機石灰を使おう
- 時間がなくて肥料と混ぜて使いたいなら有機石灰
- PH調整以外に野菜が元気に育つ効果も
石灰資材の違いを紹介しました。
苦土石灰か有機石灰を家庭菜園では選ぶようにすれば失敗は少なくなります。
土づくりが最も美味しい野菜を作るのに大切なので、良い土づくりを勉強しましょう。